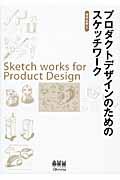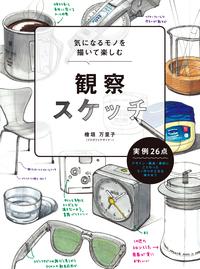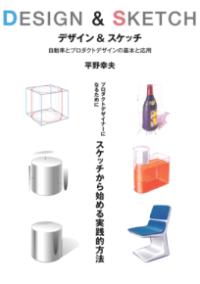デザインスケッチの勉強に使った本とか
昨夜、高校時代のチームメイトであるTomixが以下のようなtweetをしているのを見かけました。
ラフスケッチの練習したい
— Tomix (@TomiXRM) December 5, 2024
意匠が強いハードウェア設計している人みんなラフスケッチが上手いよな、やっぱりデザイン事務所でインターンとかしたら場数こなせるんだろうか
— Tomix (@TomiXRM) December 6, 2024
本人に聞いたわけではないので、彼のツイートの真意は不明なのです。が、私はこれをみて、私自身がこの夏スケッチの勉強を少ししていたことを思い出しました。
だからといって特別上手くなったわけではないのですが、良い勉強でした。
そういうわけで、彼に頼まれたとかでは全くないのですが、当時利用したいくつかの資料をまとめておくことで先人たちから受けた恩を送ることにします。
なお、本稿では「スケッチ」の語をもっぱら物理的な製品の核心的なアイデアを記録、伝達したり、意匠を検討するためのメディアとして描画されるものの意味で使います。
より広範な絵画のクラスとしてのスケッチにも学ぶべき点は多い[1] が、本稿の主な対象ではないのでご留意を。
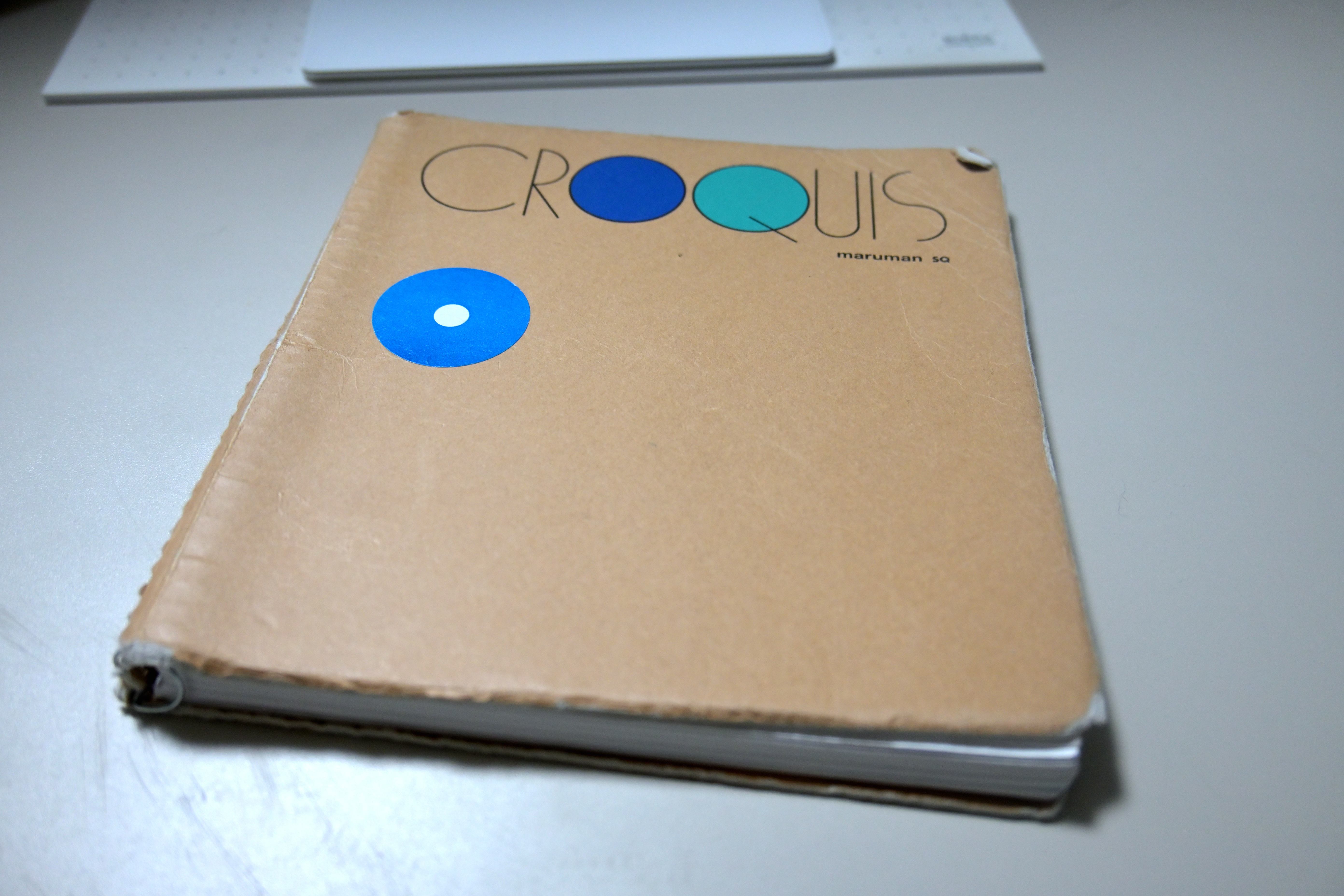
#きっかけ
私がスケッチの学習に手をつけようと思ったのは、今年の夏、UC BerkeleyのSummer Sessionに行った ことがきっかけです。
この中で、Prototyping and Fabrication(DESINV22) という授業を受講しました。
授業は、こんな感じ。(1単語分だけ私も出演している。)
授業では、3D プリンタやレーザー加工機などのおなじみのデジタルファブリケーションの技術の基礎から、それを使ったRapid prorotypingに基づくデザインのプロセスを取り扱いました。
その中で、Chris Myers先生(めちゃくちゃ褒め上手。“Good design is less design” と “Iterations!!” が口癖)が、スケッチをして見せてくれたり、スケッチの描き方についてちょっとしたワークショップをしてくれたりしました。
そこで勉強を進めるうちに、「スケッチはおもしろ工作おじを目指す上での基本スキルだろうな」と思ったので、今のうちに身につけておこうと、勉強してみることにしました。
#リソース色々
在米中は主に先生に色々聞いていたのだけれど、帰国後は本を読んでみることが学習法のほとんどの部分を占めました。
先生に聞いた部分はあまり再現性がないので割愛して、読んだ本(+動画)を紹介します。
#『プロダクトデザインのためのスケッチワーク』
ケーススタディが充実していたのが良かったです。
遠近法や投資図法などのパースの取り方が主な話題でした。
絵を描くのが好きだけど得意というほどでもない私が、基本的語彙や前提となる知識を整えるのにはちょうど良かったです。
デザインという領域は芸術領域から工学領域にかけて広がる広範な概念ですが、工学畑出身の人間に特にお勧め。
#『プロダクトデザインスケッチ : デザインの発想から表現』
こちらは、表紙にあるような色彩に富んだスケッチにまつわる話題が多かった印象です。
陰影の入れ方とかがよく説明されていたので、レンダリングを作る時には参考になるかも。逆に、その場でザクザク描いていくようなスケッチに関する話題は少なかった印象です。
#『スコット・ロバートソンのHOW TO DRAW : オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く方法』
書誌情報(国立国会図書館には書影がないらしい)
Amazon
これは、かなり汎用的なスケッチの本です。地力がつく感じ。パースの勉強をするには一番役に立った気がしますが、ちゃんと分厚いので、完走はしてません。
中で出てくるエクササイズはかなり有用なのですが、個々のエクササイズが無限に凝れてしまうので、どこで次に進めるかが難しかった印象です。
#『気になるモノを描いて楽しむ 観察スケッチ』
これは、描き方というよりは、スケッチする上でどんな部分に注目するかの点で参考になりました。
絵だけ眺めていても面白いので、パラパラとめくっていけるのも良い。
#『だれでもデザイン』
日本のデザインイノベーション界隈では大・著名人であるところの山中先生の本です。
この本はスケッチの勉強をしようとはとは無関係に読んだのですが、スケッチの話が出てきます。
山中先生といえば、今年開催されていた「未来のかけら」展はすばらしかったです。
その中でも、デザインスケッチに関するワークショップをされていたようで[2] 、ていねいなレポート を書かれている方がいらっしゃいます。
それから、TEDxでの以下の講演も、その場で描いている臨場感が伝わって刺激的で、モチベーションが上がりました。
山中先生のスケッチの話題は、スケッチを単に伝達のためのレンダリングに留めず、描く人本人の思考の場としても捉えている点が一貫していて素敵です。
Berkeleyで学んだときもやはり思考の場としてのスケッチの使い方を学んで感銘を受けたので、どうも私はこのスタイルが好きなようです。
Instagramにもたくさんのスケッチが上がっているので、楽しい。
#気になってるけどまだ読んでない本
#Sketching: Drawing Techniques for Product Designers
なんかいい噂をたまに聞きます。(読んでないからそれ以外に言うことながない)
カーリルの情報ではつくば周辺には蔵書がなさそうなので、どこかに行った時に探してみます。
#自動車とプロダクトデザインの基本と応用 : DESIGN & SKETCH : プロダクトデザイナーになるためにスケッチから始める実践的方法 新装版
なんかこの記事を書いていて、そういえばちゃんとNDLで検索はしてなかったなと思った[3] ので、検索してみたら出てきました。
なんか良さそうですね。(読んでないからそれ以外に言うことながない)
#まとめ
この手の記事は実は世界初ではなくて、例えばこれとかもそれ系の記事です。
他にもいくつかあるので、興味があれば探してみてください。
他にもいろんな本やWebサイトを見たり読んだりした気がするのですが、今覚えているのはこの程度なので、思い出したら追記します。